そして、道真公没十数年後、大阪天満宮で流觴曲水の宴が、豪快にも小川ではなく大川ではじまりました。杯の変わりに、船に大勢の人を乗せ、水納祭としました。 行事の思いは、人間と自然の関係にほかなりませんが、曲水の宴の形は大きく変わりました。 そして、時期も梅雨が終わろうとし、台風が上陸しようとする頃に、大阪らしく盛大な日本独自の祭り文化として誕生しました。
平安時代は、日本の歴史の中で唯一、死刑のなかった時代でした。 特にこの時代、人は死んでからも人を呪い、祟ることができると強く信じられていました。 菅原道真は民間出身でありながら右大臣まで昇りつめた人物です。 菅原道真の立身出世を嫉む者も多く。 ついには、太宰権師に左遷されてしまいます。 二年後の九百三年、帰京の日が来るのを待ち望みながら失意のうちに五十九歳の生涯を閉じます。 その後、菅原道真を左遷したであろう貴族達はおろか皇太子まで亡くなります。 さらに、会議中の清涼殿に雷が落ち死傷者を出します。 ここに至って、これは、菅原道真の祟りに違いないと考えられました。 そのため長岡京の都は、たった十年で終わります。
そして、菅原道真公は、雷と結びつけて祭られるようになります。 その後、道真公が祭られた天満宮では、道真公の怨念を鎮めるために、宮中行事の中で道真公が最も楽しみとした流觴曲水の宴を行うようになります。 今日、太宰府天満宮では、そのままの宴で残り、前述に記しましたとおり大阪の天満宮では天神祭り船渡御として形を変えて残っています。 また、天神祭りが、七月二十五日に行われるのは、雷の多い月であり、二十五日は菅原道真公の誕生された日、左遷された日、亡くなられた日でもあるからです。
私は、タイミングよく、その年、天神祭船渡御に参加する機会を得ました。 そこで、道真公を祀った御輿を乗せた神船に何度かすれ違うことがありました。 道真公が、曲水の宴を偲び、杯の代わりに自らを浮かべ、楽しんでおられるのではないかという現実離れをした思いにふけりながら、不思議な数時間を過ごしました。 それだけに、二日後の朝刊の各紙の記事には、大変興奮することになりました。 そして、八月一日の日曜日さっそく日本最古の宴跡を見に行きました。 大きく取り上げられたにもかかわらず、私が訪れていた間には、誰一人、宴跡を見に来る人はいませんでした。 絵に描いたように美しい夏空の下で、すでに土をかぶせられた曲水の宴を、所々に覗く石頭だけがおぼろげに物語っていました。
ここで雛人形二千三百年の時空の旅は、曲水の宴が、日本独自の文化へ進化する時を迎えます。
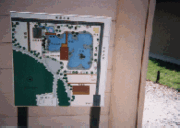
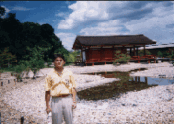

(平城宮東院庭園跡日本最古の曲水の宴跡平成11年8月1日)
日本のある地域では、三月三日に天神さんが飾られています。 中には、正月に飾るところもあります。女の子にはお雛さまを飾り、男の子には、天神さんを飾るところ。女の子でも、お雛さまでなく天神さんを飾るところ。と地域によってまちまちに風習が残っています。
私は、雛人形の時期に天神さんを飾る地域があり、また、販売しているところがあることが不思議でした。
しかしながら、道真公と曲水の宴の深いかかわりから見ますと不思議なことではありません。
道真公は、学者の家に生まれ、学問に優れた人物に育てられました。 そして、その才能は、宮中でいかんなく発揮されました。 そのため、死後は、学問の神様としても祀られました。 その神様が、最も好まれた曲水の宴を催される上巳の節句三月三日に道真公にあやかって、子供が、学問に優れた人物になるよう、国を救い民を救う人物になるよう願いを込めて天神さんを祀ったのでしょう。 また、この時期は、気候の変わり目で、病気悪癖がはびこる時期です。 天神さんの縁の地域では、これも道真公の祟りと考え、その怒りを静めるため道真公を厄払いの上巳の節句に、家に祀ることによって、祟りから子供をまもろうとしたのかもしれません。
平安時代の天才菅原道真公の生涯は、波乱万丈でありました。 死後も貴族だけでなく庶民の間にも影響を与え、今日でも天神さんとして祀り崇められているのです。
